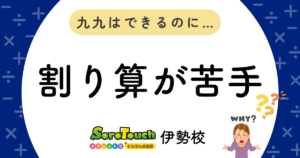子どもが割り算でつまずいたら、まず知っておきたい4つのこと
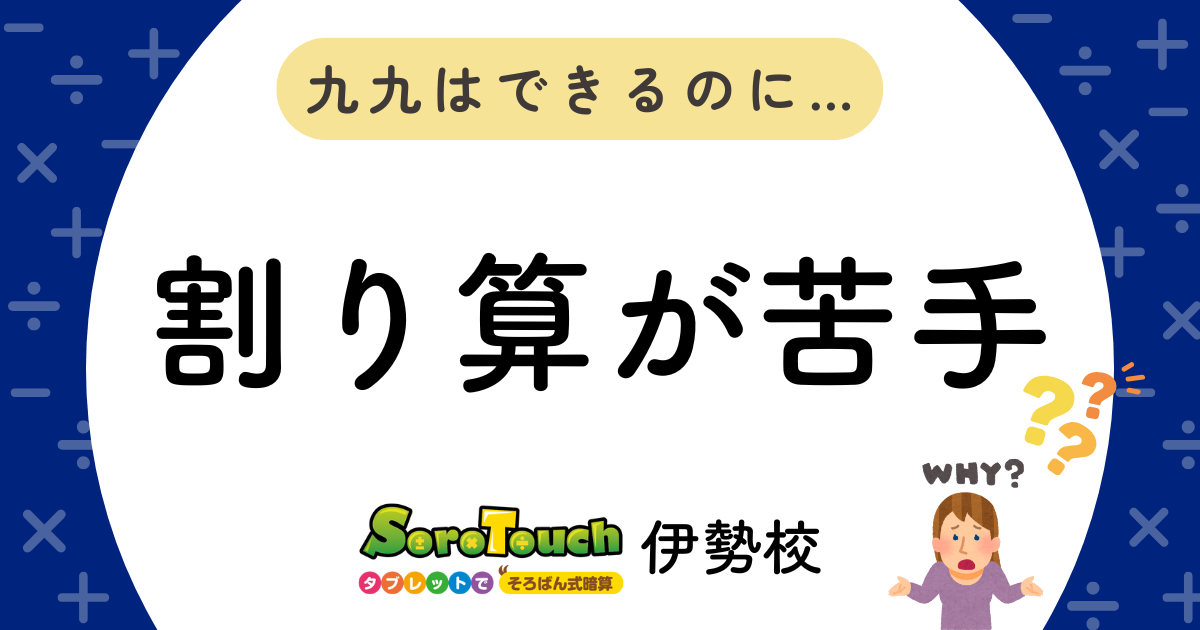
 ママ
ママたし算・ひき算・かけ算まではスムーズだったのに、割り算に入った途端、手が止まってイライラしたり、突然泣き出したり…。



九九は完ぺきなはずなのに、なぜか割り算は全くわからないというんです



これらは、よくあるご相談なんです。
ここでは、そろタッチ教室の現場で多くの子どもたちを見てきた立場から、割り算が“ちょっと特別”な理由と、親としてできる関わり方についてお話しします。



これを読めばきっと、意識が変わります。
割り算がほかの計算と違う理由
そもそも、たし算・ひき算・かけ算はある程度のルールや法則を覚えてしまえば、後はスピードや精度を高めるだけ。
- 「5のペア」や「10の友だち」を覚える
- 九九を丸ごと暗記する
- パターン認識で自動化していく
そろタッチを毎日やっている子たちは、練習量もしっかりあって計算処理能力は育っています。計算間違いはあったとしても「わからない!」ということではないんです。
でも割り算は違います。
割り算は“思考型”の計算
これまでのように「覚えたことを淡々と処理すれば終わり」という単純な構造ではなく、考えて・仮説を立てて・検証するという、ステップの多い「思考型」の計算にあたるのが割り算です。
- 商を立てる(推理する)訓練
- それをあってるか検証する訓練
これらが必要になってきます。①で推理して立てた商で計算してみて②検証。それでもあってなければまた①からやり直し。



それを何回も繰り返すので、できないー!!となってしまいがちなんです。
割り算がつまずきやすい「4つの壁」
割り算が他の計算と違うのは、以下のような“複合的な負荷”があるからです。
- 推理力が求められる
- まず「どのくらいで割れそうか」を自分で仮定し、商(答え)を立てる力が必要
- 検証のプロセスが必要
- 立てた商が正しいかを、かけ算と引き算で確認
- 思考の流れが複雑になるぶん、頭の切り替えと集中力も必要
- わからない経験に戸惑う
- 今まで順調に進んできた子にとって、割り算は久々に直面する「つまずきポイント」
- ひさしぶりに出会う「できない」の壁に、混乱や癇癪が出やすくなる
- スピード脳とのギャップが生まれる
- たし算やかけ算で「高速処理」に慣れている子ほど、割り算でスピードが落ちることにストレスを感じやすくなります。
“わからない”経験に戸惑う
九九を覚えたりそろばん式の運指を学ぶJステージでは苦労したものの、ある程度アプリの操作や指の動かし方そろタッチとの付き合い方も自分でコントロールできるようになった子たちにとって、割り算は久々に直面する「つまずきポイント」です。
それまでの計算では、「分かる」「できる」が当たり前だった子ほど、
「なぜこんなに難しいの?」「どうして答えが出ないの?」
と、自分の力に対して不安を感じやすくなります。



思考のプロセスが必要な割り算は、一筋縄ではいかぬ厄介な相手なんです。
中には「やりたくない」「わからない」と言って急に手が止まる子や、ふてくされたような態度をとる子もいます。
けれど、それは「成長が止まった」わけではなく「次のフェーズに出会った証拠」、保護者の方にはこの期間をレベルアップするための過渡期だと理解しておいてほしいと思います。
ここで大人が「なんでわからないの?」「そんな問題、簡単でしょ?」と思ってしまうとその思考は態度にでます。子どもはますます自信を失い、計算自体を嫌いになる恐れもあります。



九九は全部分かってるのに何で?!なんで分からないってなるの!?!!ってなるのもわかります。
むしろ「これはちょっとパズルとかクイズみたいだね!!」と解くことをワクワクするような表現で共感しながら、割り算という新しいチャレンジに寄り添う姿勢を持ってもらえたら嬉しいであす。
親としてできるサポートとは?
割り算の壁にぶつかったとき、保護者としてできることは“焦らず、観察すること”です。
たとえば、
- 「どうしてその答えにしたのか?」と聞いてみる
- 商の立て方のプロセスを言葉にしてもらう
- 検証の途中でミスしていないか一緒に確認する



このように、一歩引いて子どもの思考を“見える化”してあげると、どこでつまずいているかが分かりやすくなります。
思考が止まってるのか、試行が止まってるのか、九九が出来てないのか、引き算が間違ってるのか、保護者の方も推理し検証しましょう。
苦手意識を育てないために
割り算は、初めから「簡単なもの」ではないと大人が理解しておくことが重要です。
苦戦している姿を見ても、「他の子はできているのに」などと比較せず、「あ、今ここでしっかり考える力を育ててるんだな」と前向きに捉えること。
また、割り算に時間がかかる時期は、どうしてもテンポが悪くなったように見えがちです。でも、それこそが「処理型」から「思考型」への大きな転換点。ここを乗り越えれば、子どもは計算という枠を超えた“考える力”を身につけていきます。
最後に
「九九はできているのに、なぜ?」という問いの答えは、決して「能力が足りないから」ではありません。割り算は、他の計算とまったく同じやり方では通用しない、“ちょっと特別な計算”なのです。
一見すると後退しているように感じる時期も、見方を変えれば飛躍の前触れかもしれません。子どもたちは今、脳の使い方を一段階ステップアップさせようとしている最中です。



割り算の成長点は突然来ます。
九九のインストールに時間をかけたのと同じように、割り算の習得(推理・検証・試行)にも少し時間をあげてください^^