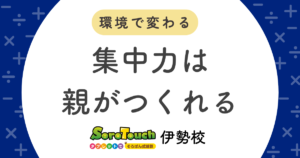勉強は「根性」じゃない!子どもの集中を邪魔する環境と整え方のコツ
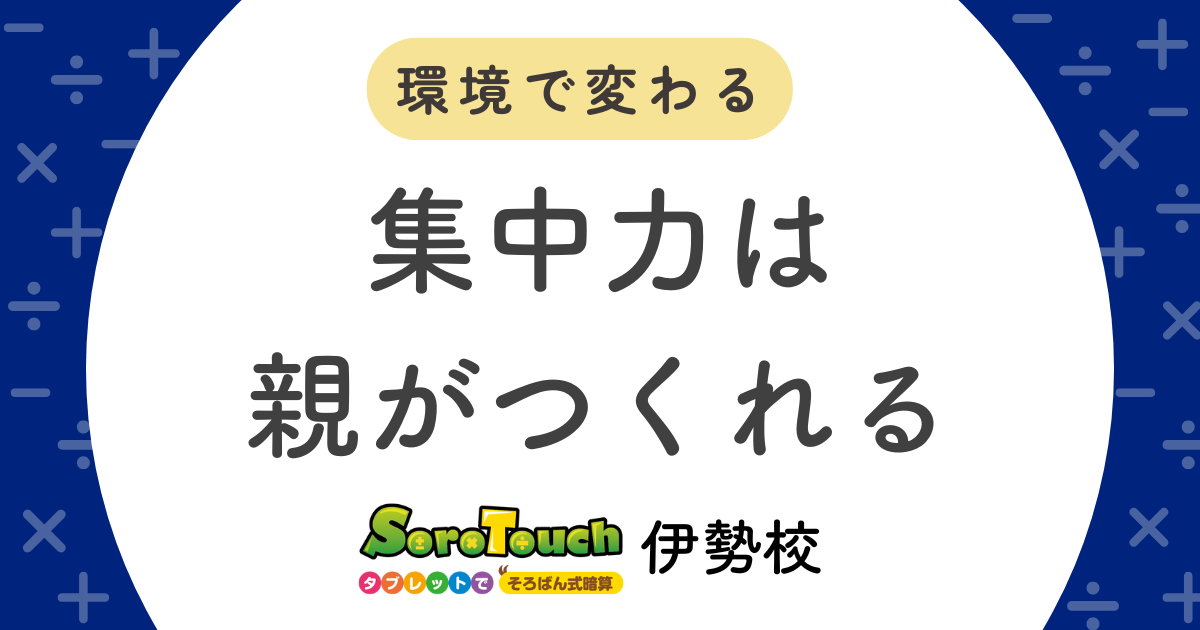
 ママ
ママうちの子、集中力がないんです



すぐ他のことを始めてしまって…



そう悩む保護者の方は多いですが、実は“集中できない子”なんて、ほとんどいないらしいです。
「集中力がない」は間違い?!
神経科学の研究によれば、集中力に関わる脳の前頭前野(前頭葉)は、12歳頃までに発達が急速に進むそうです。
この時期の子供たちは外部からの刺激(音や目に入る情報)に特に影響を受けやすく、環境によって集中力の発揮度が大きく左右される!といわれています。
集中力はトレーニング可能なスキルであり、適切な環境とルール設定があれば、ほとんどすべての子どもが集中できる
教育心理学者エリック・ジェンセン『脳が育つ学びの場』(Teaching with the Brain in Mind)
多くの場合、集中できていないのは本人の根性や意識が足りないのではなく、集中しづらい状態に置かれているだけかもしれません。
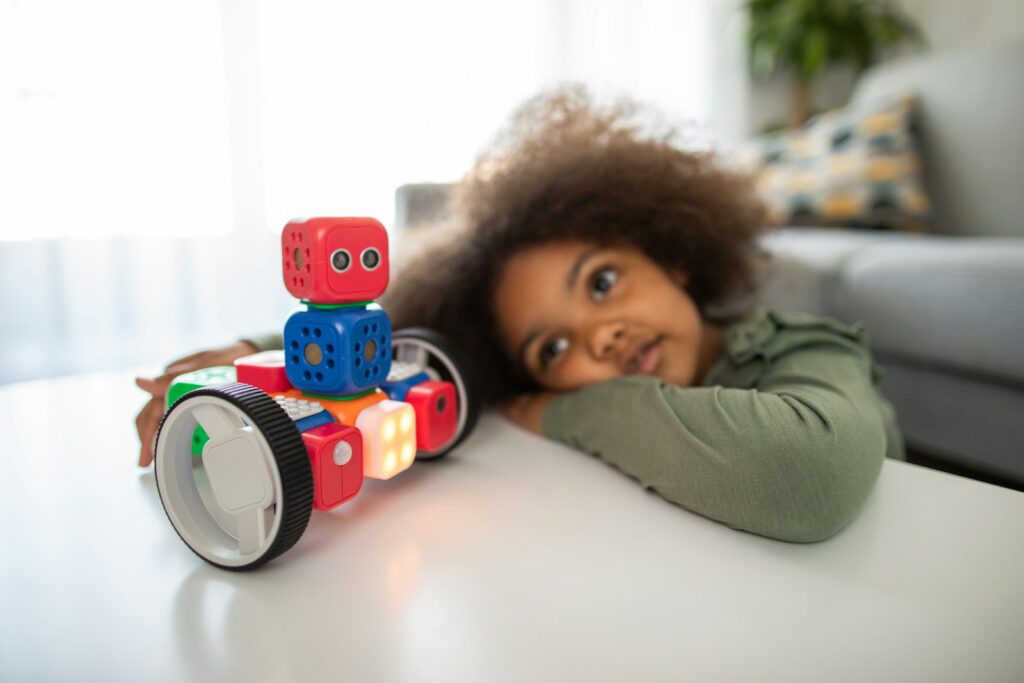
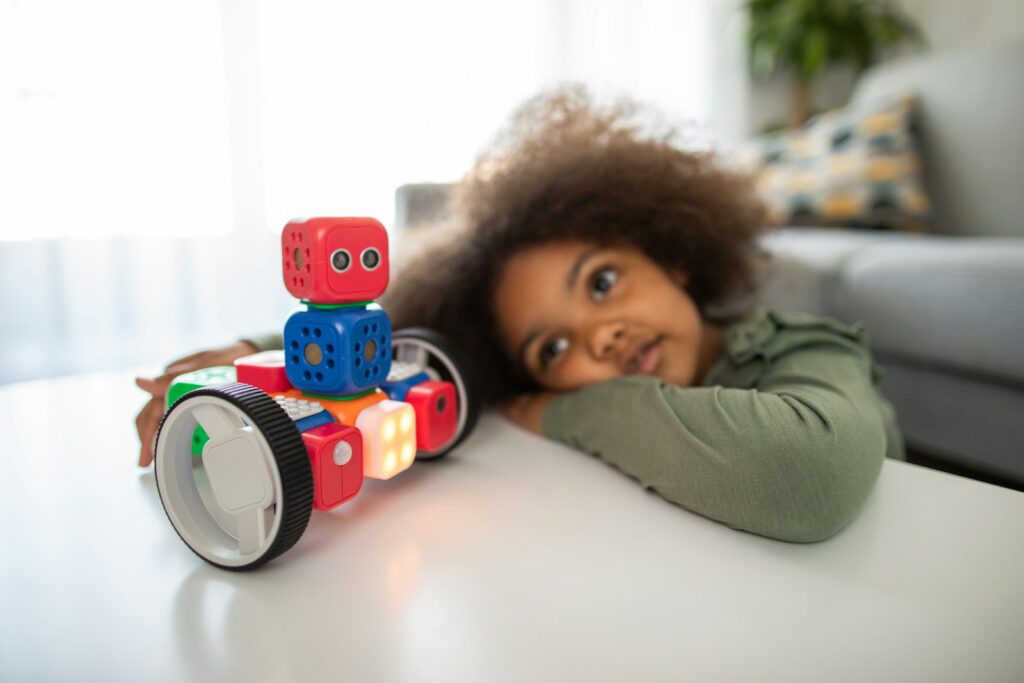
集中力を妨げるよくある環境要因とは?
視覚的ノイズが多すぎる
学習スペースの近くにおもちゃが並んでいたり、テレビや派手なポスターなどが目に入る位置にあると、子どもは無意識に注意をそちらに奪われます。



確かに・・・窓に向かって机を置いてるから、外の景色が気になってるのかも。
大人でもスマホが視界に入るだけで集中力が下がるという研究があるほど。視界の情報を減らすだけで、集中力はグッと上がります。
勉強のために知育ポスターなどが簡単に目に入る環境を作ってるご家庭も多いと思いますが、チラ見で自然と情報を入れたいのと、集中してほしいは対局にあります。
「集中スペース」は、勉強机とは別で用意するのもいいかもしれません!
音の刺激が強い・不規則
テレビの音、家族の会話、外からの車の音など、聴覚的な刺激も集中の妨げになります。
特に“聴覚優位”の子どもは、ちょっとした音にも気を取られてしまうため、学習中の「音環境」には特に配慮が必要です。



この辺りは顕著に出るお子様も多いです。



伊勢校生には学習のデータ分析をしているので「リスニング問題」「読み問題」別の正解率をグラフで確認し、対策を練っています。
大人も集中できない環境で、子どもにだけ求めていないか?
そもそも、子どもが勉強しているそばで、親がスマホを触っていたりテレビをつけていたりすること、ありませんか?



それで「集中しなさい」と言われても、子どもにとっては不公平に感じるものです。



一通りの家事が終わってため息交じりで洗濯ものを畳んでる時に、ソファーでスマホをいじってるパートナーに「おい、やる気出して集中して畳めよ?」とか言われたらどう思うかを考えると分かりやすいかもしれません(笑)事件になるww
私たち大人でさえ、周囲に雑音や気になるものがあると仕事に集中できません。子どもはなおさらです。
集中できないのは、性格ではなく環境のせいかもしれない。この視点を持つだけで、子どもへの声かけが変わってくるし、私たち親のイライラも少しは収まるかもしれません。周りの協力も必須です。
集中しやすい学習環境を整えるヒント
1
集中空間をつくる
広い机や静かな個室でなくてもOK。大切なのは、視界が限定されていること。パーテーションやブックスタンドで区切るだけでも、“学びのための場所”という意識が生まれ、集中モードに入りやすくなります。


2
タイマー活用
「15分だけ集中しよう」と時間を区切ることで、子どもは“集中する意味”を意識しやすくなります。タイマーや砂時計を使うと視覚的にも分かりやすく、メリハリのある学習習慣がつきやすくなります。


3
“できた”を共有
学習の成果を言葉で共有する経験は、モチベーションの維持にもつながります。「終わったら教えてね」と一言添えるだけでも効果があります。是非そのタイミングでは手を止めて一度向き合ってあげてください!


環境整備はコスパが高い!
環境を整えることは“学力格差”を埋める最強にコスパがいいんです。



近年の教育格差研究では、「家庭での学習環境の質」が子どもの学力形成に大きく関与することが明らかになっています。
ここで言う“環境”とは、高価な教材や設備のことではなく、照明・音・空間・声かけの質のこと。つまり、お金をかけなくても“工夫”だけで集中力は育てられるということです。



これは、家庭教育において最も“効果対コストが高い投資”のひとつです。
環境が変われば、子どもも変わる
「集中しなさい!」という叱咤よりも、「集中できる場所を一緒に作ろうね」という寄り添いの方が、子どもには何倍も響きます。集中力は性格や根性ではありません。整えられた環境の中で、自然と育つ力なのです。



もし今、「うちの子、集中力がない」と感じていたら、まずは学習環境を見直してみてください。
たった1つの小さな工夫が、子どもに「自分は集中できる」という感覚を芽生えさせる第一歩になるかもしれません。