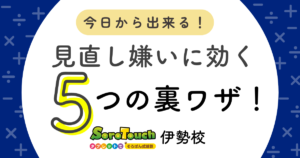見直し嫌いを変える5つの裏ワザ
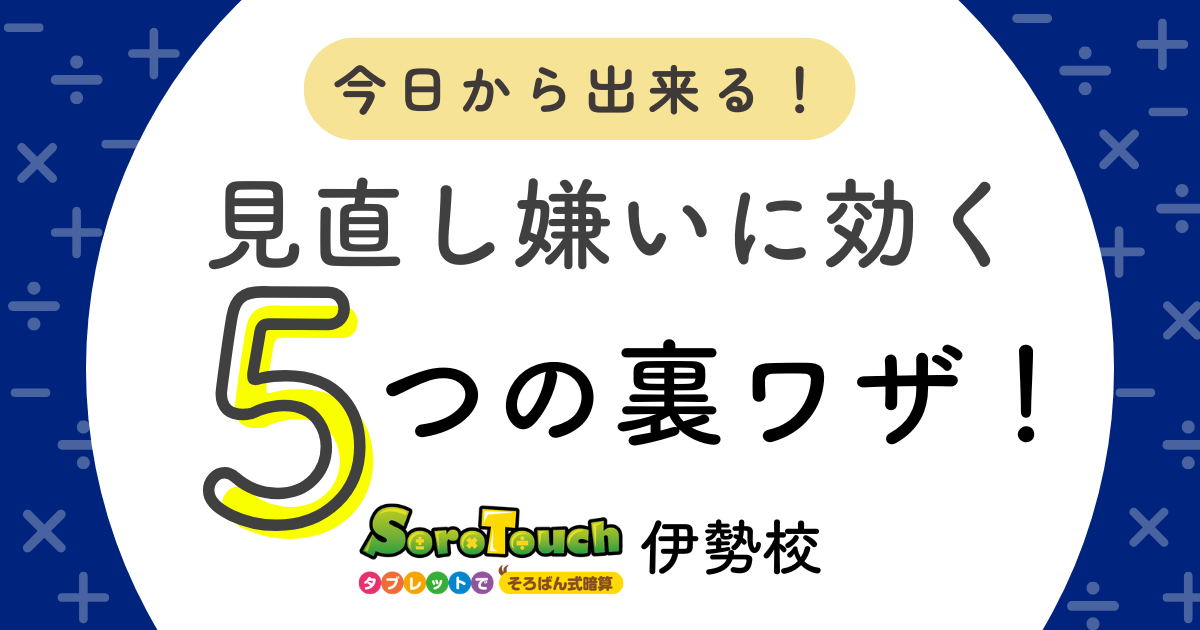
「見直し、ちゃんとしてきた?」 そう聞くと、自信満々に「やったよ!」と言っても、実はまったく見直していなかった…
どうしてこんな簡単な計算ミスに気付かないの・・・・(゚д゚#)そんな経験みなさんあると思います。(ない方はそもそもこの記事を読まれていないはず・・・!)
 いおり先生
いおり先生昭和世代に懐かしい顔文字でお届け中です(笑)
そろタッチを検討中の保護者の方からも「うちの子、計算はできるけど見直しが苦手で…」という声をよく聞きます。
この記事では、なぜ子どもたちは“見直し嫌い”になるのか、その理由と、誰でも自然に「見直す子」になれる5つの裏ワザをご紹介します。
なぜ「見直し嫌い」な子が増えているのか考えてみる
間違い=失敗だと思ってるから
間違えたら怒られる、叱られる、がっかりされる…そんな経験がある子どもは「見直し=間違いを探す作業=ダメな自分を確認する時間」と受け取ってしまいます。



大人でも間違うといつもネチネチ言ってくるパートナーや、上司、先輩がいたら、失敗を報告するの躊躇いますよね。
叱られたくないから見直す!という罰則方式では、焦りながらのミス探しなので正直しんどいですし、段々見直すこと自体がストレスになってきます。
その②:早く終わらせたいから
「計算が終わった!=解放感!」この気持ちは大人にもあります。子どもにとっては特に強く、計算が苦手だったり時間がかかる子ほど、「終わったからもうOK!あー、開放された!!」という思い込みが見直しを遠ざけます。


見直し力を育てる5つの裏ワザ
① 間違うこと=悪いことではないと伝える



まずは「間違えることは悪くない」と明確に伝えましょう。
間違いは“伸びしろ”です。たとえば、算数の問題で「4+5=8」と答えてしまったとき、「なんでそう思ったの?」と聞きながら、間違いに至った思考の流れを一緒にたどってみてください。そこには“惜しい工夫”があるかもしれません。子どもが「次はこうしよう」と自分で修正できるようになるきっかけになります。
問題なのは「間違ったままにしておくこと」であって、間違うこと自体が悪なのではありません。私たちは機械じゃないですし、私たちが目指すのは100%正解することではなく、それに向けて正解率をあげることです。
② 終わったあと“1分だけ見る”習慣をつける
「見直ししてね」と言うと、子どもには抽象的すぎることがあります。例えば「タイマーを1分だけかけて、その間だけは間違いがないか探そうね」と伝え、全部を見直す習慣を一気に目指すのではなく、スモールステップでまずは見直すという行動に慣れていくところからはじめたいです。
③ 気づけたらハナマル!自分で直せた喜びを強調
例えば、見直しの中で自分で「−1と書くつもりが+1にしてた!」と気づいた場面があったら、「よく気づいたね!!!」と声をかけましょう。
見直しを「できなかった証明」ではなく「成長できる場所」と捉え直すことで、間違いを恐れずに向き合えるようになります。ハナマルやスタンプなど、視覚的なごほうびも効果的です。
④ 「正解」より「考え直せたこと」を褒める
たとえば、問題を間違えて解いた後、「何でそう思ったの?」や「この答えになったのはどこを間違えたんだろうね?」と問いかけてみてください。すると、子どもが“自分の考え方”を言葉にする練習になります。そのプロセスこそが見直しの核心です。
「答えが合ってたね」ではなく、「気づけたことがすごいよ」「前より深く考えたね」という言葉の方が、子どもは伸びます。
名探偵コナンが好きな生徒さんは「小五郎のおっちゃんならミスに気付かないけど、コナンや平次なら気づくはず!」と血眼になって探しています。



そうやって好きなことと結びつけるのもいいですね!
⑤ 保護者が“見直ししている姿”を見せる
子どもは大人の行動をよく見ています。
たとえば、
- 買い物リストを見て「何か買い忘れてないかな?」と声に出して見直す
- LINEのメッセージを送る前に「ちょっと読み直してみよう」と口にする
- 小学校や園からのプリントを「もう一度見直そうっと!」とブツブツいう
こうした何気ない行動が、子どもにとって「見直しは特別なことではない」「大人もやっている自然なこと」とインプットされていきます。親の“生活の中の見直し”は最高の教材です。



親にとってもいいこと尽くしです!(笑)
そろタッチで「見直し習慣」が自然につく理由
ミッション形式で毎回“やり直し”がある
そろタッチは「1回やって終わり」ではなく、毎日のミッションで繰り返しに自然と取り組む設計です。見直しが特別なことではなく当たり前なので“習慣”として根づきます。



計算スピードが速くなってくるとミッションの中でも答えを押す前に見直して確認している子もいます。
ステージ制で“変化と成長”が見える
1回で正解するより、「昨日はできなかった問題が今日はできた」など、自分の変化を見られるステージ設計が、見直し意欲の原動力になります。
間違いは自動でフィードバックされる
そろタッチでは、間違えた問題をすぐにやり直す設計になっているため、「間違い=悪いこと」ではなく、「間違い=もう一度チャレンジできること」と捉えやすくなります。
見直しは“伸びしろ発見タイム”
見直しは、できていない自分を責める時間ではありません。
「見直す=自分の成長を確認する時間」 そんなふうに捉えられたとき、子どもは見直しを怖がらなくなります。大人の価値観をまず変えていくのもだいじです。 一つひとつの裏ワザを、日々の声かけや習慣づくりの中で少しずつ取り入れてみてください。



見直しは“直す作業”ではなく、“育つ瞬間”なのです。
大人が「早くしなさい」を繰り返していると「正解することより早く終わらせること」を重要視しはじめるので、自分も言ってるかも・・と思う人はここも私たちにとって見直すチャンスです!
計算スピードと正確性というのは、どちらも相反する考え方なのに、同時に求めてしまいがちです。今はスピードが要る時期なのか、スピードを落としてでも正確性を求める時期なのかそこの見極めも非常に大事です。



伊勢校生は大丈夫!私がついてます!