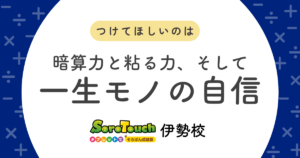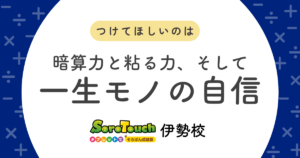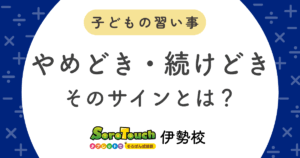子どもの習い事、やめどき・続けどきのサインとは?教育視点で見る“今”の見極め方
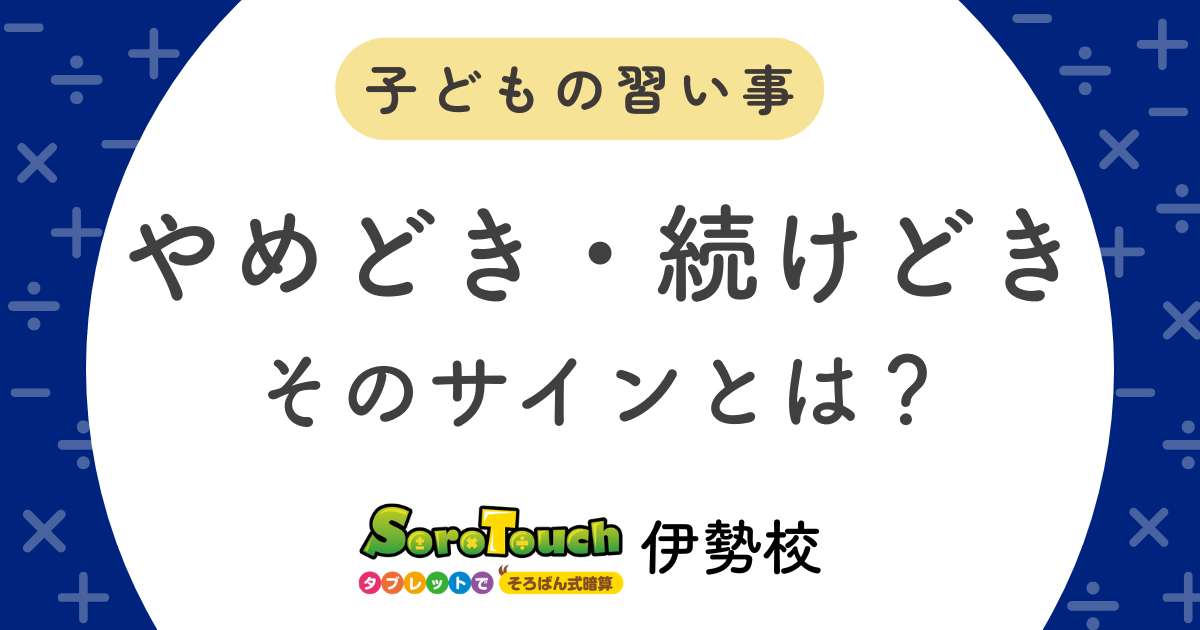
 ママ
ママ周りはどんどん進むのに、なかなか思ってるように成果が出ない・・・このまま続けてても意味ある…?



始めた当初みたいに本人のヤル気が見えないんだよな…



習い事をやめるべきか、続けるべきか。保護者にとってはとても悩ましいテーマですよね。



でに親の判断ひとつで、子どもの未来が変わるような気がして、なかなか決断できないです



分かります。お金も時間も体力も精神力も有限、でも子供の将来が大切だから迷う・・・・。
けれど最近の教育研究では、「やめる・続ける」は“成果”だけで判断するのではなく、“育っている力の質”や“本人の感情”まで含めた総合判断が望ましいとされています。
習い事を続ける価値は「見えない力」にある
スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授が提唱する“成長マインドセット”理論では、「結果が出るかどうか」よりも、「試行錯誤を続けた経験」が子どもの粘り強さや自己効力感を育てると指摘されています。
さらに、ハーバード大学の研究では「習い事を通じて得た“継続の記憶”が、学力やキャリア形成に長期的な影響を与える」とも。



つまり、続けた事実そのものが、子どもにとって自信の土台になっていくのです。



結果がまだ見えなくても、「今はまだ育っている途中」かもしれません。
続けた方がいいサインとは?
1. 子どもが“完全に嫌がっていない”
「行きたくない」とは言わないけれど、テンションが低いし「楽しかった?」と聞いても「ふつう」とそっけない。そんな微妙な反応に、親はつい「続ける意味あるのかな…?」と不安になってしまいます。



でも、“嫌がっていない”という事実は、実はとても重要なサインです。
人は、本当に嫌なことに対しては行動を拒否します。泣いたり、逃げたり、寝たふりをしたり、腹痛を訴えたり……。何かしらの“防衛反応”が出てくるものです。



けれど、多少気が進まない様子があっても自分で準備して教室に向かっている、あるいは声かけすれば動ける、という状況であれば、その習い事が「拒絶するほど苦しいものではない」可能性が高いといえます。
また、子ども自身が「うまくいっていない自分」にモヤモヤしていたり、成長の“停滞期”にいるだけであることも多くあります。心理的には不安定な状態でも、実は内側では学びが進行している“沈黙の成長期”とも言われます。
この時期に親が「やめる?」と先回りして判断してしまうと、「頑張ってるのに伝わってない」と感じさせてしまうことも。様子を見ながら、本人が本音を出せるような関係を大切にしつつ、“まだ自分の中で頑張る意味を持っているかもしれない”という前提で接することが大切です。
2. 小さな変化・成長が見える
たとえば「授業でもよく先生に話しかけるようになった」「宿題や課題を前より嫌がらずするようになった」など、スキル以外の行動変化が見られるときは、“育っている途中”です。
心理学ではこのような行動面の変化を「情緒的成長」と呼び、特に自信の芽生えや環境への安心感が生まれているときに見られる特徴とされています。
テストの点や成果だけでなく、「教室での過ごし方」「先生との距離感」「自分の態度の変化」などにも注目してみてください。それらはすべて、子どもが今“育っている”証拠です。
3. 自分で準備したり、終わったあと満足げだったりする
目立った成果がなくても、自分から動いている姿勢や「今日もがんばった」という表情があるなら、それは心が前を向いているサイン。支える価値があります。
「今日は●●教室だよね」「◯時になったら出発しよう」など、自ら準備する姿が見られるようになったら、それは内面的なモチベーションが育っている証拠です。また、教室からの帰り道や終了後の表情が明るかったり、「今日はここができたよ」と話してくれるようになっていれば、子どもは“取り組んだこと”に満足している状態にあります。
発達心理学では、自分で準備する・報告する・振り返るという行動を「自己決定的行動」と呼びます。
これは、子どもが「やらされている」状態から「自分の意志でやっている」状態に近づいているというサインでもあります。こうした兆しが見えているなら、結果が出ていなくても、習い事がその子にとって“意味ある活動”になっている可能性が高いのです。
やめどきを考えるサインとは?
1. 身体や心に無理が出てきている
帰ってくるとぐったりして寝てしまう、食欲が落ちる、笑顔が減る、教室が始まる前に急にお腹が痛くなる――こうした身体のサインは、言葉よりも早く“もう無理かも”という心の声を表していることがあります。



特に子どもは、自分の感情をうまく言語化できないため、「体調が悪い」などのかたちで不調を訴えるケースがよくあります。
保護者としては、「疲れてるだけかな」「最近忙しかったし…」と見逃してしまうこともありますが、心と体はつながっています。
もちろん単純に肉体的に疲れている場合や、不調の原因が習い事ではなく学校や人間関係に起因している場合もあります
継続的に「習い事の前だけ」同じような反応が見られる場合は、少し立ち止まり、子どもの“身体の声”に耳を傾けてみてください。



習い事が“頑張る場所”であることは大切ですが、“無理をして耐える場所”になってしまっては、かえって自己肯定感を下げることになりかねません。
2. 本人が「苦しい」と口に出し始めている
ミスを強く叱られたり、クラス内の人間関係が悪かったりすると、習い事そのものが自己肯定感を下げる場になってしまうことも。
出来なくて感情的になって「辞めたい」と言ったり「もう嫌だ!」ということは案外出来なくて悔しい悲しいが根本原因なので、「辞める」=最適解でないことが多いのですが、本気で「苦しい」「辛い」と言い始めたときはかなり危険なサインかもしれません。
ここで重要なのは、まず“苦しい”という言葉をすぐに否定しないことです。



ついつい甘やかさないように「頑張りなさい」「わがまま言わないの」「みんな頑張ってる」と返してしまいますが、そうすると子どもは“本音を言っても受け止めてもらえない”と感じてしまい、心を閉ざしてしまいます。



グッサグッサ刺さります・・・。ダメだと分かっているんですが、1000万回ぐらい私も言ってます・・・(反省)



・・・



まずは「そっか、大変だもんね」と共感し、理由を丁寧に聞いてあげましょう。
また、理由がはっきりしていないこともあります。「なんとなく嫌」「行きたくないけど理由がわからない」そんな場合でも、いったんペースを落としたり、習い事以外の生活に目を向けたりすることで、子どもが自分の気持ちを整理しやすくなることもあります。
3. 教室との相性に疑問がある
習い事を継続するうえで、“教室との相性”は実はとても大きなファクターです。
- 先生の対応が気になる
- 周りも含めて成果があまり見えない気がする
- 教室に励みになる上級者や憧れが居ない
- 子どもが先生とあまり話したがらない
子どもにとって先生は、“その習い事を象徴する存在”。先生の話し方や雰囲気、フィードバックの質は、子どもが「ここにいてもいい」と感じられるかどうかに直結します。
保護者から見ても、「話しかけづらい」「質問しても曖昧な返答」「やたらと成果ばかりを強制する」など、信頼関係が築けない教室に対しては、自然と不安が大きくなっていきます。



この辺りの話題は私も他人事ではない話題です・・。
一方で、成果を急がず、日々の変化を丁寧に見守ってくれる教室であれば、多少停滞しているように見えても“育っている”時間を安心して過ごすことができます。



けど個人的には「遠くから丁寧に見守る」だけなら、逆を返せば先生何も仕事してないんじゃ?とも思います。状況を打破する対策は適宜しっかり提示したりしてほしい!
「相談すればちゃんと向き合ってくれる」「誠実に子どもと関わってくれている」「親の気のゆるみも含めて淀みをしっかりとかき混ぜてくれる」と感じられる教室なら、信頼をもって続けていける環境だと言えるでしょう。
“やめどき”は、子どもだけの問題ではなく、教室との信頼関係のバロメーターでもあります。



別に悪い先生じゃないけど、なんとなくモヤモヤする・・・けど理由が言語化できない
本人が「先生がこわい」「話したくない」と感じている、または保護者としても「成果に納得できない」「先生に相談しづらい」「連絡が雑」「説明が不透明」「誠意を感じない」といった不信感がある場合、それはやめどきを見直すひとつの指標です。



子どもはとても敏感です。信頼できる先生・安心できる環境があってこそ、学びは前向きに続いていきます。



耳が痛いです!肝に銘じます!!
4. 別の目標に向かいたがっている



最近、ピアノよりも絵を描くことに夢中みたい



今は凄い勢いでプログラミングに興味を持ち始めてる
子どもの興味関心は、成長とともにどんどん変化していきます。そしてこれは、決して“飽きっぽい”だけなのではなく、“視野が広がっている証拠”でもあります。
発達心理学では、ある分野に一定期間取り組んだことで、子どもの内面に「自分は何が好きか、どんなことにワクワクするのか」という感覚が芽生え始める時期があるとされています。



つまり、ひとつの習い事にしっかりある程度の期間打ち込んだからこそ、次に目指したい方向が見えてきた――ということもあるのです。
また、「嫌だから辞めたい」ではなく「次はこっちをやってみたい」という気持ちが見えてきたなら、それは単なる逃避ではな、【主体的な進路変更】の兆しとも言えます。



もちろん、どんなに興味があってもすべてに手を出すのは難しいですが、そのときに「何かを手放して、何かを選ぶ経験」は、子どもにとって大きな自己決定の学びになります。
親としては「せっかく続けてきたのにもったいない」と感じるかもしれません。でも、それまでの経験は決してムダになりません。音楽で培ったリズム感がスポーツに活きる、暗算で育てた集中力が将来の学習に役立つなど、“点と点がいつかつながる”のが子どもの成長です。目の前の選択を肯定的に受け止め、次に進む勇気を支えてあげられるといいですね。
「目に見えない自信」を育てている
うちの子、空手、習字も英語もやりたいっていったから始めたのに結局大泣きして嫌がってすぐに辞めちゃったけど、唯一スイミングとそろタッチ教室だけは幼稚園の頃からずっと続けてこれてて。この前お友達のママに
「俺は泳ぐのと計算はずっとやってきてる!幼稚園からずっとだよ!だからめっちゃ得意!!」
と話してて、やっぱり色んな習い事を辞めたことは本人の中でも残ってて、だからこそ続けられてるスイミングとそろタッチがとっても大事なんだなーとしみじみ思いました。
本人も気づかないうちに、「私は○○を続けている」という事実が自信になっていることはよくあります。それを手放したとき、思いのほか心がぽっかりすることも。だからこそ、辞めるときには「やめたあとも安心できる居場所があるか」「本当に他の選択肢が必要なのか」をていねいに確認してみてください。
習い事は「目的」ではなく「手段」
- この教室は、先生に相談しやすい
- 子どもの変化に気づいてくれる
- 無理に一律で成果を求めない
- 習い事に行くこと自体を拒絶していない
- 終わった後は楽しそうにしている
- 実際に始める前と比べてかなりスキルが上がっている(他人とではなく過去の我が子と比べる)
そんな環境であれば、少し悩みがあっても“続けていく価値”は充分にあります。



習い事は、結果を出すための場所ではなく、“子どもが自分らしく学べる場所”であるべき。だからこそ、辞めるときにも、続けるときにも、親子で納得できる選択をしたいですね。
そもそも習い事は、子どもの才能や自信を育てるための“手段”です。無理に続けることが目的になってしまうと、本来の意味を失ってしまいます。やめることも、続けることも、どちらも間違いではありません。



私たち親ができるのは、子供の成長や感情を丁寧に見守り、表情や言葉にちゃんと耳を傾けること。それがお互いにとって“納得のいく選択”につながっていくんだと私は思っています。(道半ばです(;^_^A)